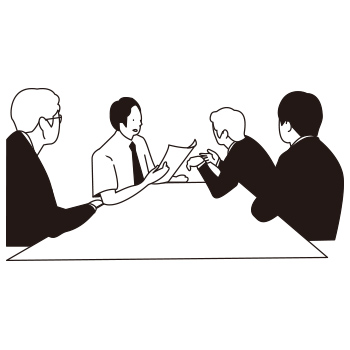映画を観に行く前
中学2年生の時、近所の内山写真館の一人息子である同級生の内山祐一君(同じ野球部でセカンドの名手でもあった)から筆者への誕生日プレゼントとして『Sheer Heart Attack/ シアー・ハート・アタック (1974年)』を頂いたのがクイーン初体験である。
おそらく(先行発売されたシングルの)『Killer Queen』あたりをたまたま一緒に(ラジオで)聴いていて、娼婦の歌だということも知らずに「なにこれ、カッコいい!」などと新潟の片田舎で一緒に盛り上がっていたのだろう。実際に“針を落として”ぶっ飛んだのはA面1曲目の『Brighton Rock』だ。ここで初めて、ブライアン・メイ(Brian May)の洋風津軽三味線の洗礼を受けたわけである。
筆者は、ロイ・トーマス・ベイカー(Roy Thomas Baker)が中心になってプロデュースしたものこそがクイーンだ、といまだに信じている古いファンだ。初期クイーンの音楽性の特徴は、
1)シンセサイザーを利用しない(No Synthesizers)
2)アナログテープのマルチトラック録音での分厚いコーラス
3)ギターオーケストレーション
の3点にあると思うが、この音作りはロイの技術力やセンスによるところが大きい。プロデュース業の先輩であるフィル・スペクター(Phillip Spector)の「Wall Of Sounds」をかなり意識していたはずだ(ただし、2のマルチトラック録音における技術的最高峰は、間違いなく10ccの『I’m Not in Love(1975)』だろう)。
従って、『A Night at The Opera / オペラ座の夜 (1975年)』までの4枚と、再びロイが陣頭指揮を取ることになる『Jazz / ジャズ(1978年)』の計5枚こそが、筆者にとってのクイーンである。『A Day at the Races / 華麗なるレース(1976年)』、『News of the World / 世界に捧ぐ(1977年)』の2枚(マイク・ストーンの協力によるセルフプロデュース)は音の立体感やメリハリが強すぎる、いわゆる“オーバープロデュース”が鼻につき、個々に良い楽曲はあるものの、アルバムとしての完成度が高いとは言い難い。プロデューサが違うと別の音楽になることを教えてくれた最初のミュージシャンがクイーンだった、とも言える。
クイーンがライブバンドだと思ったことはないし、コンサートに出向いた経験もない。そもそも、先に紹介した3つの音楽的特徴をステージで再現するのは無理である。また、出回っているライブ映像で確認した限りにおいて、フレディ(Freddie Mercury)がその“4オクターブの声域”をフルに活かしたボーカルを披露したことは一度もない(初期のツアーで喉を壊したのでステージ上では封印していたはず)。すべての楽曲において、フレディの声域はなるべく狭い領域で再現するように編曲されていて、高音域はロジャー(Roger Taylor)が担当している。当然“美しいハーモニー”とは言い難い。
また、初期の楽曲が全編にわたって演奏されることは非常に少なく、今回の映画のタイトルにもなった『Bohemian Rhapsody』などの名曲も、メドレーの一部として断片的に再現されるに過ぎない。ステージ上でのフレディの振る舞いがカッコいいのは確かだが、ライブならではの聴きどころはむしろ少ないバンドである。
初期のクイーンファン同様、筆者も、仰々しさ満載の『Queen II / クイーン II (1974年)』を絶賛する一人だ。デビュー・アルバム『Queen / 戦慄の王女(1973年)』のリリースからわずか1ヵ月後に彼らはこの2作目の制作に着手した(一作目の録音からリリースまでの期間が異様に長かったという事情による)。全編にわたって24チャンネルのマルチトラックレコーダー(MTR)が大活躍する。当時のアナログLPのA面に該当するブライアンによる優雅なWhite Side (White Queen)と、B面を支配するフレディ率いる悪の軍団的Black Side(Black Queen)という構成が、オモテとウラがあるLPの魅力を最大限に引き出していた。
特に、同じ曲のエンディング部分のテープ逆回転からスタートする『Ogre Battle』をこけら落としに、曲間を最小限に短くしメドレー形式で展開、スマッシュヒットになった『The Seven Seas Of Rhye』で大団円を迎えるBlack Sideは、同じように評価の高いThe Beatlesの『Abbey Road / アビイ・ロード(1969年)』のB面と比較しても遥かに優れた音楽劇(theatrical)になっていて、翌年発売されることになる『A Night at The Opera』よりも、こちらのほうがよほどこのタイトルに相応しい。
このアルバムは、最終的に全英5位にチャートインする出世作となり、そこから慌ててファーストアルバムを買った人も多かったようだ。クイーンの最高傑作は『A NIGHT AT THE OPERA / オペラ座の夜』だということになっているが、筆者にとってはこの『Queen II / クイーン II 』こそが全てである。
『The Game / ザ・ゲーム(1980年)』は、ロイと袂を分かち、かつ積極的にシンセサイザーを利用した音作りに向かうことで、よりファンの層を広げることになる最初の作品だが、このあたりから、筆者にとってのクイーンはどうでもいいバンドの一つに成り下がった。ジャケット裏の目立たないところに「No Synthesizers」とクレジットし、自らストイックな制約を課して音を作ろうとするところにある種の美学を感じていたのだが、その制約から解き放たれたクイーンのようなバンドは他にいくらでもあったのだ。ただ、この頃からフレディとブライアン・メイのバンドだったクイーンが、本当の4人のバンドになって、より幅広いファンにアピールするようになったのも確かなのだろう。
さらに80年代は、音圧を上げた録音が流行し、猫も杓子もシンクラヴィア (Synclavier)かフェアライト(Fairlight CMI)を利用するようになり、“平均的に良い音楽”が圧倒的なボリュームで量産されていくデジタルレコーディング時代の幕開けでもあった。70年代の音楽はいくらデジタルリマスターしたとしても70年代を感じさせるが、80年代からは「これはつい昨日録音したものだ」と言っても通用するくらいに経時劣化を感じ取るのが困難になった。
もはや録音技術で検討すべきは、ハイパーソニック・エフェクト(Hypersonic effect、注1)の処理くらいしか残されていないのではないかと思えるくらい進化がいきなり頂点に達してしまったのだが、筆者にとってのクイーンはこのあたりで終わりである。ロックミュージックというもの自体に興味を失い始める一方、新しい分野の音楽との出会いが始まっていたのだと思う。
91年にフレディの死亡を告げる記事を新聞で見かけた時は「ああ、そういえばこんなバンドあったなぁ」と久々に思い出して、追悼の意味も込めて「The Game」以降にリリースされた何枚かをCDで購入したが、あまり真面目には聴いていない(ただ、『INNUENDO / イニュエンドウ(1991)』に収録された『The Show Must Go On』での鬼気迫るボーカルは感動的)。
一般にミュージシャンの私生活は、その創作活動のためにドラッグや、グルーピー(groupie)との乱痴気騒ぎ、そして酒に溺れるデタラメなものになるのが常なので、その印象的な死因についても特に意外性は感じなかった。従って、現在公開中の映画はおそらく自分にとってはさほど面白いものではないだろうと想定すると同時に、この予想が見事に裏切られることも期待していたわけである。
映画を観終わって
映画の中で流れる楽曲は、その大半がオリジナルをそのまま使っていて、かつ、それらが丸ごと再現されるというよりは、断片的なエピソードとして挿入されているに過ぎないため、音楽そのものを楽しむ映画でもなければライブ感を共有しオーディエンスとして参加する映画でもない。むしろ、フレディのバイセクシュアリティ(bisexuality)と、出自や容姿に関するコンプレックスや葛藤をストーリーの軸にしつつ、どの程度“本物に似ているか”に徹底的にチャレンジした映画、と割り切ればそれなりに良くできた映画である。
特に、ステージパフォーマンスにおける(フレディ以外の)ダサい部分(e.g.とても華麗とは言い難いジョン・ディーコンの体の動き、など)を忠実に再現しているのが微笑ましい。フレディの両親など本人かと思うくらいそっくりだし、1970年代当時のロンドン周辺の雰囲気を再現することに随分コストをかけているのもわかる、という具合に、とにかく徹底的に「似せる」ことに労力を費やした映画である。
『Bohemian Rhapsody』が(演奏時間が)長すぎることでラジオのオンエアを拒否されそうになる、というような、ファンなら誰もが知っているエピソードもきちんとそこかしこにフォローされている(この時、引き合いに出された前例がRichard Harrisの『MacArthur Park』であることにもきちんと言及している)。観る側も、そのあたりを存分に楽しむ、というスタンスで臨めば満足度が高いだろう。
フレディのステージ上ので有名なパフォーマンスに、観客との「エーオ!」というコール&レスポンスがあるが、劇中では、HIV感染の診断を下され落胆したフレディが病院を後にしようとする直前に、それがフレディであることを発見した、廊下のベンチに佇む(クイーンの熱烈なファンと思われる)患者から、か弱い声で「エーオ」と声をかけられ、立ち止まって、少し躊躇してからフレディがやはり小さな声で「エーオ」と応えるという印象的なシーンがある。
実はこれが、なかなか感動的な伏線になっていて、この映画が売りものにしようとしているラストのLIVE AIDではこの「エーオ!」を数万人の観客に対してフレディから“力強く”コールするわけだ。むろんフィクションのはずだが、この映画の白眉は、意外なことに、この病院での名もない患者とフレディのたった二人の静かで短いやり取りにあるように思う。
劇中では、HIVに感染したことをきっかけに、最後の力を振り絞ってLIVE AIDで素晴らしいパフォーマンスを披露したかのように構成されているが、LIVE AID(1985年)に出演したときフレディはまだ発病していない。「少し前までは栄華を誇っていたかもしれないが、最近はすこし落ち目で、解散するかもしれないくらいパッとしない過去のスター」と思われていたバンドが意外といいパフォーマンスをした、というのがこの時のクイーンに対する一般的な評価だ。
実際には、70年代の業績に対する賛辞だったのだと思うが、これに彼ら自身が勇気づけられ、翌年(1986年)の、最大にして最後のパフォーマンス 「Live at Wembley ’86」につながるのである。つまり、この映画の最大の見せ場が事実とは決定的に異なるにもかかわらず、このあたりを割り切った上で、チコちゃん流「たぶんこうだったんじゃないか劇場」がまことしやかに、そして見事に展開されている。でたらめなストーリーに“真実”を語らせる力があるのが映画というメディアの凄まじさだ。
2回、3回と見れば、その度に新しい発見がありそうなおもちゃ箱のような映画ではあるが、通常は1回見れば十分だろう。感動を呼ぶというよりはごく単純な(ファン向けの)娯楽映画だと割り切ったほうが妙に落胆せずに楽しめる。また先に述べたように、楽曲そのものの再現性はあまり重視されていないので、ScreenXやIMAXでの上映にこだわる必要はない。
しかし、映画を観終わってから、評判の高いボブ・ラドウィック(Bob Ludwig)による2011年のデジタルリマスター版を5、6枚買い直したりしているので、素直に術中にはまっている自分がそこにいたりはする(注2)。
注1)
人間の耳の可聴領域は、通常、20Hzから20,000Hz程度(高い周波数ほど歳を重ねると聞こえにくくはなる)で、鼓膜の振動を音として認識している。しかし、この領域を超えて生体が反応しているケースが多く観察されていて、骨や皮膚などが、これらの音を拾っている可能性があることが指摘されている。風力発電の風車のそばに放牧されている牛の発育に問題があるという指摘があるが、これはタービンから発生する低周波が牛の何らかの感覚器官に直接悪影響を及ぼしているのではないかと言われている。一方で、20,000Hzを超える領域における音が人間の活動や脳の状態に心地よさを提供する場合がある、というのがハイパーソニックエフェクトだ。日本の楽器では琵琶や尺八がこれを発生する。サウンドスケープ(soundscape)への応用なども期待されていて、音からの心地よい街づくりに貢献できる可能性がある(参考文献:『ハイパーソニック・エフェクト』大橋力(2017年、岩波書店))。
注2)
少々持ち上げすぎな文章が鼻につく部分もあるが、日本語でのクイーンのディスコグラフィーについてはユニバーサルミュージックが運営する「クイーン:アルバム制作秘話」が一番参考になる。

- 書名
- 会社をつくれば自由になれる
- 出版社
- インプレス/ミシマ社
- 著者名
- 竹田茂
- 単行本
- 232ページ
- 価格
- 1,600円(+税)
- ISBN
- 4295003026
- → Amazonで購入する → Kindle版を購入する