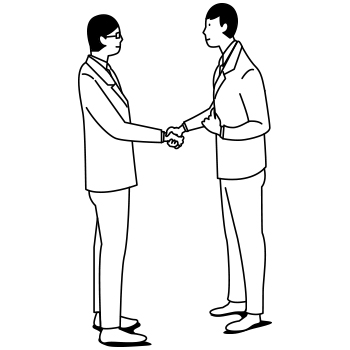肩書きなんぞ汎用性の低い一種の無形文化資産(遺産?)に過ぎないのだが、その中でも「執行役員」はかなり微妙な肩書きだ。
執行役は比較的最近耳にするようになった肩書きだが、これはれっきとした役員である。取締役も当然ながら会社法上の役員である。しかし両者を兼ねる肩書きのように見える「執行役員」は身分としては単なる従業員に過ぎない。会社法上は何の意味も権限もない無価値な言葉である。
付与する立場からすれば、こんなにお気軽な肩書きはないのでガンガン乱発できる。何しろ筆者の会社にも一人いるくらいである。ある程度の規模の会社になると、至るところに所在なさそうな執行役員がウロウロする光景を目にすることになるだろう。
帰宅して「今度の人事で執行役員になったよ」と奥さんに報告すれば赤飯を炊いてくれるかもしれないし、それはそれでめでたいことなのかもしれないが、「役員」という言葉の響きの良さに最後まで幻惑され続けることになるはずだ。執行役員の大半は、その上に控えているであろう取締役になることはなく、関連会社へ転籍するか、そのまま定年を迎えるはずである。
しかし「自分は曲がりなりにも執行役員まで務めた人物なのだ」と一念発起して起業してみたりする。そしてここから悲劇が始まる。
特定の企業内で付与される肩書きは、あくまでその企業の中におけるポジションの説明材料としてのローカルルールに過ぎない。そして(もちろん企業によってその扱いは色々だとは思うが)執行役員は経営の現場(e.g.取締役)にいたわけでもなければ、営業の現場(e.g.部長)を駆けずり回っていたわけでもない。
どのような現場であれ、そこを離れることで浦島太郎になるのには1年もあれば十分だ。他の役職も兼務している執行役員はまた別の議論になるが、純粋な執行役員は立ち振る舞いが規定されていないので現場が存在しないことが多い。
猛烈に動き回っている部長が勢いで作った新しい会社と、50代の数年間を現場を持たずにボヤっと執行役員をやっていた人が作った会社のどちらに発注するかと考えれば、圧倒的に前者であろう。後者は、現場を離れたうえに経営もやったことがないのに、やたらとプライドだけは高い扱いにくい社長として敬遠される可能性が高い。
従って、高齢化が進んだとはいえ、やはり部長になれる/なれないくらいの年齢の時に起業したほうが無難だろう。執行役員に就任して有頂天になっているようなヤツは、起業などしないほうが安全である。少なくとも今まではそうだった。成功イメージに「成長」などの共通認識があったことに起因する。
しかし、昨今、特に3.11以降の時代のムードの中で感じるのは、その“成功”というイメージが少しずつ変化しているということだ。成功イメージは売上ベースでいくつかのステップがある。1億、2億、5億、10億を売上のマイルストーンとして設定してみると、下記のようになる(業界や資本政策によって売上数値自体の意味は大きく異なるので、ここはあくまでイメージで捉えていただきたい)。
1億:もはや自分が個人事業主ではないことを実感する。外注費もそれなりに使う。ただしワークスタイルについては相当自由度が高い。
2億:古典的な法人形式を用意しないと運営が辛くなり始める。例えば、売上に直接寄与しない総務系の常駐スタッフが必要になってくるのがこの頃。
5億:ここを越えると1億の頃の杜撰さや自分自身が持っていた裁量権が懐かしくなる。後には引けなくなり、会社は売上を伸ばす方向でしか成長できない。上場も視野に入ってくる。
10億:会社というよりは“企業”に近い存在(=そこそこの社会的責任が発生する)になる。従来の感覚でいうとこのあたりが“成功”だろう。まずは20億を目指してフル稼働できる体制が整った、とも言える。
このように、線形な成長戦略を描き実現していくことがいわゆる成功“だった”。しかしこれからは違うのではないか。1億から2億の間くらいをウロウロしつつも沈没しているわけではない、という状態が経営者にとっては幸せな状態であり“新しい成功”のスタイルになりつつあるような気がする。
メディアからは面白くないケーススタディ(メディアは常に従来型の成功ストーリーを探している)なので記事になる機会が少ない分、現象としては確認しにくいのだが、このような地殻変動が静かに始まっているように感じる。
執行役員が起業した直後は、おそらくしばらくは失敗が続くだろう。しかし、そもそも地頭は悪くないはずなので、数年間に様々なことを考え、徹底的に学習するはずである。営業的な現場感覚も取り戻すだろう。そして“本当の起業”がスタートし、1億前後の売上で、コンサルティングを中心にした事業、あるいは請負などのビジネスが作れるように思う。古い成功スタイルの是非などについても、一定の認識・知見が形成されてくる。スケールアウトなどしなくても仕事自体を楽しめる状態こそが“本当の成功”として実感するはずだ。
以下にご紹介するのは、2012年3月に立教大学で実施された2011年度大学院学位授与式における吉岡総長の送辞である。当然、学生に向けたものであり、大学のあり方について述べているのだが、筆者にはこれからの私たちの働き方についての示唆に聞こえる。
正直に告白すると、筆者が「専門性」とか「専門家」に疑義を感じ始めたのはこの演説がきっかけだ。重要なのは「考えるという営みは既存の社会が認める価値の前提や枠組み自体を疑うという点において、本質的に反時代的・反社会的な行為」と看破しているところにある。成功という既存の価値自体も疑ってかかったほうがいいと言っているように聞こえるし、拡大解釈すれば、執行役員を卒業した人に対するメッセージとも受け取れないこともないと思うのだ。けだし名演説なので一部を抜粋・引用する。
東日本大震災が崩したのは、日常世界の物質的基盤だけではありません。日常世界を構成しているさまざまな要素に対する「信用」も失われてしまいました。現代科学の最先端領域の「専門家」たちの事故後の発言が、事態の混乱を深めるばかりであったのは記憶に新しいところです。
また、私たちは、既存の政治機構が機能不全を起こし、政治家の言動やマスメディアの報道が、事態をますます悪化させているのを目の当たりにしています。高度な研究を行っている専門家や、著名な大学の出身者である政治家への不信が広がる中で、大学という研究・教育機関への信頼が失墜していったのは不思議ではありません。いま私たちは、大学の存在根拠自体が問われていることに自覚的であらねばならないのです。
現実の社会は、歴史や伝統、あるいはそのときどきの必要や利益によって組み立てられています。日常を生きていく時に、日常世界の諸要素や社会の構造について、各自が深く考えることはありません。考えなくても十分生きていくことができるからです。あるいは、日常性というものをその根拠にまで立ち戻って考えてしまうと、日常が日常ではなくなってしまうからだ、と言ったほうがよいかもしれません。
しかし、マックス・ウェーバーが指摘したように、社会的な諸制度は次第に硬直化し自己目的化していきます。人間社会が健全に機能し存続するためには、既存の価値や疑われることのない諸前提を根本から考え直し、社会を再度価値づけし直す機会を持つ必要があります。
「考える」という営みは既存の社会が認める価値の前提や枠組み自体を疑うという点において、本質的に反時代的・反社会的な行為です。皆さんの中には、これから社会に出ていく人も、大学院生として後期課程に進む人も、また、大学や研究所で研究者としての歩みを続ける人もおられることでしょう。社会人として働きながら本学に通い、これから次のステージを目指している人もたくさんいるに違いありません。
皆さんがどのような途に進まれるにしても、ひとつ確実なことがあります。それは皆さんが、「徹底的に考える」という営為において、自分が社会的な「異物」であることを選び取った存在だということです。どうか、「徹底的に考える」という営みをこれからも続けてください。そして、同時代との齟齬を大切にしてください。
※全文はこちらへ「卒業生の皆さんへ(2011年度大学院学位授与式)」

- 書名
- 会社をつくれば自由になれる
- 出版社
- インプレス/ミシマ社
- 著者名
- 竹田茂
- 単行本
- 232ページ
- 価格
- 1,600円(+税)
- ISBN
- 4295003026
- → Amazonで購入する → Kindle版を購入する