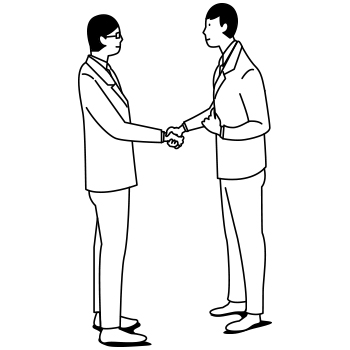コミュニケーションはざっくり言うと、ヒトとヒト、ヒトとモノ、そしてモノとモノの3形態しか存在しない(ここでいう“モノ”はとりあえずヒト以外のモノすべてを想定しているが、狭義ではmachine=機械の意味で使われることが多い)。ヒトとヒトのコミュニケーションに電話を利用させることでそれなりに儲けていた電話会社(オペレータ)は、通話してくれる人口が減少し始めてしまい通話料が増やせないので、モノとモノの通話にも課金してしまえと考えたのがIoT(Internet of Things)である、という少々乱暴な解釈も当たらずといえども遠からずだろう(このあたりの正確で簡潔な記述は古瀬幸弘氏による「この解説」が詳しいので、こちらをご参照いただきたい)。
このIoTにおいて私たちが見落としがちなのが、モノとモノはさらに2つのモノ(?)と繋がらないと実効性が薄いという事実だ。文化と制度である(さらにもう一つ付け加えるとしたら文明の集積度との接続度も重要だが、とりあえず無視)。IoTは文化や制度との接続ができて初めて実効性が伴うようになる。
例えば、AIチップを搭載した自動運転車は、センターにあるクラウドと“繋がる”ことで快適な走行が実現できるであろうと想像できるが、当然、速度制限がそこに立ちはだかる。速度制限は道路交通法という形の制度(制度は多くの場合法律の形をとる)なので、これとどのように“接続させるか”が腕の見せ所、ということになる。
モノとモノはデジタルコミュニケーションが可能だが、制度は弾力的かつ恣意的に運用されることで丸く収まることが多い。これをコンピュータが理解できる形で実装するのは困難だろう。何があろうと制限速度を遵守する自動運転車に積極的に乗りたいドライバーはいないだろう。面白くない上に危険だからだ。
例えば、トンネルの壁の崩落が始まったような状況で、猛スピードで駆け抜けないと潰されかねないときに制限速度を守るのは自殺行為である。あるいは、IoTを駆使して植物工場でレタスを作ったとして、それがとんでもなく美味であっても食品衛生管理法から逸脱しているのであれば販売できない(そんなレタスはないと思うが)。
結局、IoTといえども最後は、ヒトとヒトのコミュニケーション(あるいはネゴシエーション)で完結するらしいことが想定できる。IoTのコア技術は欧米のベンダーに抑えられてしまう可能性が高いので、日本としては「文化や制度との接続方法」で差別化要因が作れれば、それなりに商売になるだろう。IoTという“最先端”の現場で役に立つのは案外古典的な価値観だったりする可能性が(少なくとも、日本の場合は)あると思われる。
文化は“マナー”として表現されることが多く、国や地域で極端な違いがあるのはご承知の通りである。例えば、日本国内では電車の中で携帯電話を使って会話するのはマナー違反だ(これがマナーになっているのは世界広しといえども日本だけで、個人的にはまったく納得できないマナーだが)。新しい道具が出現したときにマナーがどのように発生し、どこで閾値を超え、どのあたりでロックイン(確定)し、またどのように衰退していくのかは社会学的に面白いテーマなのだが、前述の古瀬氏の記事はこのあたりのことを「社会的コンセンサス」と表現している(さすがに格調高い表現である)。
一方の制度についていえば、法律をどの程度スピーディに改定できるか、あるいは特区などの制度を機動的に設置できるかにかかっている。運用してみてダメだったらさらに改定すればいいだけの話なのだが、そのあたりのスピード感に欠けるのは日本の政治の弱点のようにも思う。
IoTはその接続対象の種類と個数が無限とみなしても構わない状態になるので、どのようなマナーや制度がどこで出現することになるのか皆目見当もつかないのだが、とりあえず社会資本(道路、橋梁、水道管、電気、ガス、工場など)の制御系のIoTでさえ、個人が所有するスマートフォンと無関係な状況にはなりにくいような気もする。オーソドックスだが、まずはスマートフォンを起点にしておくIoTがビジネスとしては比較的安全だろう。
加えて、“繋がりの品質”は実にいろいろな性能を合算した総合的なものであることに留意しておこう。通信機器に限定すれば、時間的持続性(堅牢性)、単位時間あたりのデータ転送量(強度)、データの遅延(レイテンシー:latencyという)、外部からの攻撃への耐久性などがまずは気になるところだが、これにヒトが絡むと、途端に厄介なパラメータが出現する。
「(人間関係などの)深さ」「(単位期間・時間あたりの)繰り返しの回数」「形」「匂い」「触覚」「色」「相性」でさえコミュニケーションと無関係ではない。真っ赤なポルシェを見ると山口百恵を思い出す(「プレイバックPart2」)、みたいな話も、ある世代にとってはそれもまた通信の一つである(同世代であれば、たとえ他人であろうと同じ時代の空気を吸っていたはず、という感覚だけで繋がることが可能だったりする)。
あなたがコンサルタントとして起業したとして、複数のクライアントを抱えるとしたら、それぞれとの繋がり方の多様性に面食らうかもしれない。頼まれたことを淡々と処理するだけの、医者と患者のような関係のクライアントもいれば、もう少し親しい関係になって、経営の深いところまでサポートするような繋がり方になる場合もある。さらにそれが過熱すると一種の共犯関係になってしまうことがあるので注意したい(注1)。
(経験的には)クライアントとの繋がりの強さと売上には、あまり相関関係はないように思う。「こんなにもらっていいんですかね」が1年で終わる場合もあれば、大した金額でなくても何年も付き合っている場合もある。言うまでもなく後者のような「細くとも長い付き合い」があなたの経営者人生を豊かにしてくれるだろう。
さらに、本当の長い関係というのはクライアント個人との接続ではなく、法人との堅牢な接続になるはずだ。いったん、信頼関係の構築に成功すれば、担当者が変わってもそれを理由に取引が途絶えるというリスクは激減する。担当者が変わったことによりその法人との関係が途絶えた場合は、あなたはその担当者と仲が良かっただけ、ともいえる(筆者はこれが多いのが弱点である)。
ともあれ、闇雲に人脈を広げようとする行為にはどこか貧乏くさいところがある。会話に頻繁に“人脈”が出てくるようなヤツほど自分の人間関係として繋げておきたい相手になりにくいのは不思議といえば不思議なのだが。
注1)
このあたりの話を整理したのがMITの名誉教授であるエドガー・ヘンリー・シャイン(Edgar Henry Schein)である。彼はコンサルタントとクライアントの関係は4種類あると考えた。レベル1の関係(一定の距離を置いた事務的な関係)、レベル2の関係(親密で信頼関係が強い関係)、レベル3の関係(癒着)、そしてレベルマイナス1(クライアントからみたコンサルタントが搾取の対象になる関係)である。だから何、という程度のハナシだが。

- 書名
- 会社をつくれば自由になれる
- 出版社
- インプレス/ミシマ社
- 著者名
- 竹田茂
- 単行本
- 232ページ
- 価格
- 1,600円(+税)
- ISBN
- 4295003026
- → Amazonで購入する → Kindle版を購入する