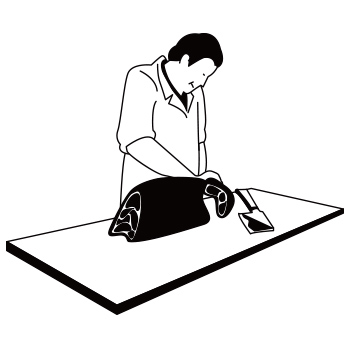文化資本を語るときにはブルデュー(Pierre Bourdieu)の少なくとも『ディスタンクシオン(distinction)』くらいは読んでおけ、というのがおそらくそのスジでの常識なのだと思うが、とりあえず文化資本(cultural capital)とは、
(1)その文化によって社会的コストを大きく下げる
あるいは、
(2)妙な儲け方を可能にする
のいずれかのための道具、あるいはその属性ということにしておく。
(1)を議論するためには、どうしても「道徳」というものを定義しなくてはならなくなるが、これも一刀両断で「道徳=倫理+法律」で構成される、ということにしておこう。倫理は個人の中にある道徳的な考え方のことを指し、社会が持つべき道徳集が法律である、とする(当たらずといえども遠からずであろう)。
法律には開発コスト、運営コスト、監視コスト、違反を罰するコストなどが必要になるが、倫理は個人に対する教育コストだけで済むはずなので、倫理は法律に比べて格段に安上がりであることが容易に想像できる。従って、同じ量の道徳を実現したいときには、法律コストが限りなくゼロに近づき、最終的には道徳=倫理になるのが理想的ということになる。
本来、法律は必要悪なのであって、たくさん立法する内閣や議員が妙に評価される社会というのは、出来損ないのプログラムにパッチ(patch)を当てまくっている状態を礼賛しているのと同じなわけで、下手な落語を聞かされてる(=笑うに笑えない)気分になるのである。
法律をどんどんゼロに近づけるための最も有力なツールが宗教だが(多くの場合、憲法が信教の自由を保障しているので、法律は宗教を制御する機能を本質的には持たない)、ここで「企業倫理」などという概念を持ち出すと話がややこしくなる。
先ほどの定義からすれば、企業は個人ではないのでそもそも倫理など存在しない。会社法という法律によってその存在を担保されているだけの集団に、個人に対して適用されるべき倫理なる概念を当てはめるとおかしなことになる。
ただし、会社が小さいほど個人と会社に区別がつかなくなるので、倫理+宗教(心)で面白い教義(dogma)を編み出したりする。どんな会社であっても、創業期のストーリー(=独自の意味性が強い物語)が面白いのはこれが理由である(注1)。
さて、倫理は“マナー”という形で可視化される。マナーが活躍している領域が広いほど法律に基づく監視などのコストは小さくなる。弁護士が不要な社会はマナーがうまく浸透していると言えるので、結果的に大きなコストダウンになる。訴訟前提社会(米国のことだが)のご機嫌をとるために法科大学院などを乱立(2004年)させてしまった結果がどうなったかは、みなさんご承知のとおりである。
一方、(例えば、だが)ブータン王国には信号機がない。犬が道路に普通に横たわっている国なので、そもそもスピードが出せないのだ。犬を轢き殺さないように通り抜けねば、という倫理を全員が持っていることも相俟って、信号機不要社会が出来上がり、社会的コストは小さくなっている、と言える。「自動運転社会」に本当に必要なのはこういう視点だろう。
だがしかし、「すでに出来上がったつもりになっている出来損ないの社会人」にマナーの重要性を訴え続けるのは、下手をすると法律制定以上のカネがかかる上に、全く効果がないことは日々報道されているニュースを読んでいれば一目瞭然だ。倫理・マナー・礼儀などの教育は可能であれば未就学児、もしくはせいぜい小学生くらいまでの間に済ませておく、それも徹底的に、という社会的コンセンサスこそが必要なのだ。
年齢の上昇とともに疾病を修復させる医療コストが急上昇してしまうので、医療の肝は予防医療(またはそのための幼少期の健康増進)にある、という話と同じである。ただし、儒教的価値観をなぞっておけばよかった昭和までと異なり、頼るべき師範や古典を見失ってしまった平成以降は、その方法論を家庭が独自に編み出す必要が出てきた。考える自由を獲得すると後が大変なのだ。
未就学児を抱える家庭は、親が独自にあるべき教育について考え、実践を繰り返さねばならない面倒くさい時代になったとも言える。ともあれ、文化資本をコスト削減に利用するのはさほど効き目がなさそうな国に(日本は)成り下がってしまったような気がする。
さて、エキサイティングなのは、(2)の「妙な儲け方を可能にする」の議論だ。そして、ここにしか日本が生き残る道はない。
これは、仕入原価に対して異様とも思える付加価値率を実現できているもの、と定義できる。「なんでそんなものにそんなお金を払うの?」と思えるようなもの、すなわち、多くの人が、機能・性能・利便性などと相対(あいたい)させても経済的合理性を感じ取ることができないものには、たくさんの文化資本が注入されている可能性が高い。
男性から見たときの(女性用の)化粧品は、その代表格だろう。とても安く仕入れることができる妙な匂いを発する化学物質(多くの場合、植物性または動物性の油脂)が、女性を美しく(最近は一部の若い男性もするらしいが)するというだけでとんでもない価格になって販売され、かつ購入するほうも納得しているのが素晴らしい。化粧品同様にコーヒーの香りなども文化資本度が極めて高いと推察できる(注2)。
最近はさらにマスカスタマイゼーションの手法(花王が言うところの「スモールマス市場」。この行き着く先がオーダーメイドである)を駆使することで、小さなクラスターに最適化し価格を吊り上げることに成功している例が散見され始めた。ここでも文化資本が活躍している。無論、化粧品やトイレタリーにしかとれない手法ではないことは言うまでもない。
極論すれば、全ての産業でこれが可能なのだ。筆者自身、「NATO=北大西洋条約機構がローライ(Rollei )にオーダーで作らせた」というストーリー(=意味)にうっとりして、明らかに価格性能比の悪い双眼鏡「Rollei 7×42」をすでに20年以上利用していたりする馬鹿者だが、満足度は非常に高い。意味の含有量が多い文化資本には価値が劣化しにくいという特徴があることを実感する。
双眼鏡「Rollei 7×42」がいまだに使えるのは、光学系だけで構成され、通電を必要としないからでもある。そもそも電気製品は文化資本になりにくい。何しろ通電しなければ使い物にならず、かつ通電するという行為自体がその電気製品の経年劣化を加速させる上に、数値で性能が簡単に比較できて、かつその利便性で勝負せざるを得ないが故に、新製品にあっという間にその座を奪われる。
ただし、電気製品に文化資本が皆無とは限らない。筆者は、社会人になってから何十台ものThinkPad(当時はIBM製)を購入したが、そのほぼ全ては(現在利用している1台を除き)使い捨て、である。ところが、AppleのSE/30(1989年発売)だけは、いまだに(すでに利用していないにも関わらず)捨てられない。この“破棄するには惜しい”という感覚は文化の度合いを測る一つの指標になりうる。かつてのAppleは文化資本(=意味)を電気製品というハードウエアの形にするのが上手だった(実際には「フロッグデザイン」の仕事だと思うが)。
文化資本には経済合理性はないが、熱狂的なファンが偏在している。ただ、それぞれのファンの人数はそれほどの数ではないので、マーケット全体への影響は限定的に見える。
ところが、である。先に述べた「どんな会社でも創業期のストーリーは面白い」を具体的な会社の存在形態と照らし合わせて妄想してみよう。1万人の従業員を抱える1社と、10人の従業員しかいない1000社(ただし、それぞれに熱狂的なファンがいるとする)の文化資本の総量を比較すると、後者が前者を上回るのではないかと想像できる(注3)。
ここで重要なのは、ファンが問題にしているのは値段ではなく値打ちだ、ということだ。値打ちには価格合理性はなく、値段より高額になることも多い(価格を設定しにくいという言い方がより正確かもしれない)。
日本は実は太古の昔からそれをやっていて、それが職人や芸人の世界で再現されている。ただし、残念ながら(文化資本の)装置化には失敗したように見えるので、それをどうやって取り戻せるかが課題である(個人的にはちょっとしたアイデアがあるが)。
職人には、二つの大きな特徴がある。まず、「企画・研究・開発・製造・販売・運用」を一人もしくはごく少人数で実施している、という点だ。裁量権がすべての業務プロセスで最大化されているので、大変ではあるがやりがいを感じやすく、また(すべてのプロセスで)次から次と新しい発見が出現するので飽きることがない(このような働き方を大企業で実現する方法が実はあるのだが、その時、既存の組織が総力を挙げて、羨望の眼差しとともにそれを潰しにかかるはずである)。
二つ目の特徴は、顧客よりは素材に関心があることだろう。どの職人も、顧客よりは素材との対話を楽しんでいるように(第三者には)見える。この素材とのコミュニケーション能力は、実は消費者もその気になれば案外簡単に習得できる。
朝ごはんにアジ(鯵)の開きが出てきたとしよう。その時に「うわ。まさかここで君に会うとは思わなかった」とアジに声をかけてみてほしい(死んでるけど)。あの大海の中を泳いでいた1尾とあなたが食卓で会う確率はほぼゼロのはずなのに、偶然会えてしまったのだ。これを一期一会と呼ばずしてなんといおう。このアジは、あなたに食べてもらうためにここまで成長してきたのである。その想いを十分に汲み取り、苦労をねぎらいながら箸をつけてみてほしい。美味しさが倍増すること請け合いである。素材との対話は、つまらない人間との事務的な会話より遥かに豊かなのだ(比較すること自体がアジに失礼かもしれぬ)。
閑話休題。話を元に戻す。文化資本は、電気製品あるいはデジタルデータと相性が(基本的には)悪い。下記は経済学者、故・内田義彦の名言だ。少々長いが引用する。
学問というのはある程度習得すれば誰でも獲得できる。その意味では“やさしい” 。しかし学問以前の社会、すなわち経験の世界(筆者注:職人のことを指している)、ここでは日常語を使いますね。この日常語は漫然としている面があるけれど、ある意味で極めて精密なんですよ。精密すぎるんだ。例えば味付けをするのに「塩◯◯グラム」なんて言わない。「適当に」というでしょう。「適当に」というのは漫然としているけれど、しかし多少とももののわかった調理人がいう場合の「適当に」というのは、「零コンマ何グラム」みたいな、そんな粗雑な言葉では言い表せないものを「適当に」味付けして、という意味でしょう。だから「適当に」ということを覚えるためには10年なら10年やってみなければわからない。
(内田義彦『形の発見』(1992年、藤原書店)
デジタル社会という言葉だけでも、もう貧乏くさいことこの上ない、ということになるわけだが、この論考では日本語という文化資本について多くのことが語られている。日本語は「漢語・明治翻訳語・和語・外来語」×「文語・口語」×「漢字・片仮名・ひらがな」の24種類の表現を一つの文章内に組み込むことを良しとする極めて複雑かつ(それ故に)孤立した言語だが、この中でも「和語」が持っている日常性が実はかなり厳しい表現だ、と指摘している。
これは私たちの“日常感覚”とは真逆だろう。例えば「密着」という漢語を和語で表現すれば「寄り添う」ということになるが、和語にした瞬間にその守備範囲がかなり広くなることにお気づきかと思う。そのような一見使いやすそうな言葉は注意して使えよ、という警鐘なのだ。会議室で飛び交う言葉に比べ、台所で交わす会話の方がより切実だ、という感覚は若い人には伝わりにくいかもしれないが、例えば会議室で飛び交う“社会”という言葉が、多くの場合、自分とは無関係な絵空事なのに比較すると、自宅で家族と交わす“世間”という言葉は、かなり具体性を帯びた真剣勝負のはず、といえばわかりやすいだろうか。
ただ、内田氏が指摘する世界に没入できる人は極めて少数だろうし、また、その必要もないような気がする。というのも、日本が古来から持っている文化資本の最大の特徴は“接木(つぎき)”にあると考えるからである。
例えば、3LDKのマンションにも和室が一つだけあるケースは多い。本来、それが本当に“マンション”なら和室など存在しないはずだが、日本のマンションには必ずと言っていいほど和室がある。このとき、和室自体が「和風」の象徴なのではなく、「洋風のものに、本来異質なはずの和室を導入して悦に入っている」のが和風なのである(すべてが和風の場合は“これは純和風”という具合にいちいち断りを入れるはず)。
和風とは、本来接続されないはずの妙なものを繋いでしまうなんとなく貧乏くさい文化資本のことなのだ。ただし、ここに適宜うまいストーリーや意味を挿入していければ、ガイジンにもウケて儲かる手段になるやもしれぬと考えれば良いのである。
この観点から先ほどの内田氏の指摘を受けての今後の対応策を考えると、「デジタルテクノロジーと自分自身の技量を接木することで、データ化されない豊かな技能を誇っている職人」の姿が浮かび上がることになる。政府が「デジタル経済、フィンテック、AI、オープンイノベーションを推進する」と海外に決意表明して時間稼ぎをしてくれている間に、庶民はデジタルも含めた接木に勤しめば良い。そこから出現する文化資本はなかなか真似をしにくい固有の価値を創出することになり、それが「日本が生き残る道」になるような気がする。
注1)
筆者がこの論考でオッカムの剃刀(Occam’s razor)を駆使していることにお気づきだろうか。仮定の数をどんどん切り落としていくと、議論が鮮明になって、わかりやすくなるのである。無論この剃刀は“諸刃の剣”でもあることにも留意しておきたい。
注2)
これを「エロティック・キャピタル(The Power of Erotic Capital)」と呼んだのがキャサリン・ハキム(Catherine Hakim、共同通信社、2012)だ。言葉はセンセーショナルだが、論考自体は真っ当な文化資本論である。
注3)
このあたりの論考はすでに2年以上前に書いた「10万社の新しい中堅企業」を参考にしていただきたい。

- 書名
- 会社をつくれば自由になれる
- 出版社
- インプレス/ミシマ社
- 著者名
- 竹田茂
- 単行本
- 232ページ
- 価格
- 1,600円(+税)
- ISBN
- 4295003026
- → Amazonで購入する → Kindle版を購入する